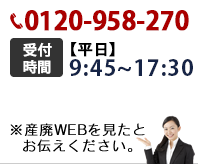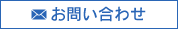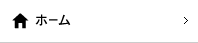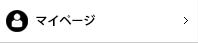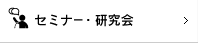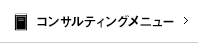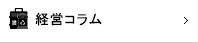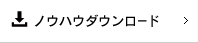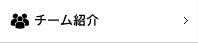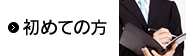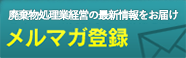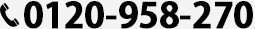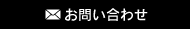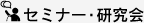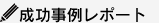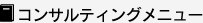経営コラム
廃棄物処理業は、サーキュラーエコノミーの潮流に如何に取り組むか⑧
2025年のサーキュラーエコノミーの取り組み方についての第8弾となります。
今回は、廃棄物処理業者が気になる、「廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令」についてとなります。
先ず最初に、「環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるもの」「環境大臣は、判断の基準となるべき事項を勘案して、必要な指導及び助言をすることができる」と続きます。そして気になる「環境大臣は、特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況が、判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる」とあります。「環境大臣は、勧告を受けた特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる」「特定産業廃棄物処分事業者は、毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った数量及びその再資源化を実施した数量を環境大臣に報告しなければならないもの」へと続いていきます。
つまり、特定産業廃棄物業者になるか否かで、今後の取り組み方を考える必要があるわけですが、この背景には国が資源循環産業のあるべき姿への道筋を示し、再資源化に消極的であった廃棄物処分業者も含めて、産業全体を底上げを図るものがある為でもあります。
特定産業廃棄物業者は、「年間の処分量が政令で定める要件に該当するもの」として、以下の要件案が示されています。
一 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が10,000トン以上であること。
二 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること
この基準となると、15条での焼却施設の大半が該当しますし、廃プラ1500tでもそれなりに該当することでしょう。何の基準か気になるところで、その考えは以下の通り記されております。
・ 再資源化の実施の促進のためには、国内の産業廃棄物の処分量を広く設定することが望ましい。一方で、産業廃棄物処分業者は、従業員数10人未満の比較的規模の小さい企業が6割強を占めているため、勧告・命令及び報告義務の対象となることによる産業廃棄物処分業者の負担も考慮する必要。
・ そこで、比較的規模の小さい企業を除く3割程度の企業を対象とする前提のもとで試算すると、年間の産業廃棄物処分量が10,000トン以上の者が全体の約27%で、処分量全体の約93%を占めているため、これを要件とする。
・ ただし、廃プラスチック類については、再資源化の実施の需要があるにも関わらず、容積に比して重量が軽いため上記要件では対象とならない者が多数出てくることを踏まえ、別に要件を定めることとする。
・ 具体的には、上記要件と同様の考え方に基づき試算すると、年間の廃プラスチック類の処分量が1,500トン以上の者が全体の約25%で、処分量全体の約89%を占めているため、これを要件とする。
つまり、「小規模業者は手間が掛かることを免除しますが、それなりの会社は取り組んでください」とのことで、それがこの規模レベルではないかと推測のように出されている数値です。勿論、まだ確定ではないものの、再資源化率を上げる為にはプラ新法だけでは難しく、更に強制的な仕組みが必要と考えているのかもしれません。カーボンニュートラルの潮流からも当然ではあるものの、インセンティブ型での難しさから、強制型に舵を切っているようにも感じております。ただ、その流れは止まらないわけですので、如何にビジネスチャンス化させるかが重要になっていくと思います。