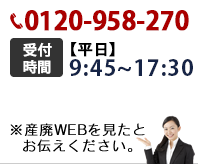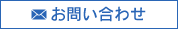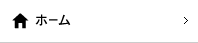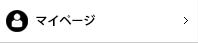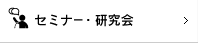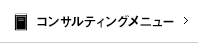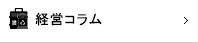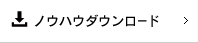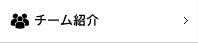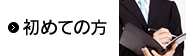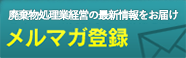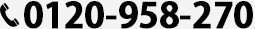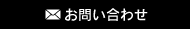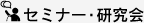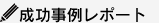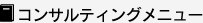経営コラム
廃棄物処理業は、サーキュラーエコノミーの潮流に如何に取り組むか⑥
2025年のサーキュラーエコノミーの取り組み方についての第6弾となります。
前回までの通り、2025年にサーキュラーエコノミーでのビジネス展開として、おさえるべき「高度化法」こと資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律についてとなります。前回の認定基準について、続きとなります。
前回の通り出口ありきであることは、リサイクルの根底になって久しいと思います。しかし、出口に流れていても、本当に意義のあるリサイクルであったかは疑問が残るものも発生していきました。リサイクルをする為に、多量にCO2を排出していれば、本当にリサイクルが正しかったかにもなっていきます。それ故、認定基準にある通り「事業シナリオ」と「基準シナリオ」があるのですが、それは同機能の製品を製造したシナリオとの比較となります。その同機能の製品の考え方には、カーボンフットプリントの考え方準用するとなっております。現在、SCOPE4とも言われる削減貢献量の議論よりは多少余裕があるものの、それでもこれまでのリサイクルについての課題には一歩踏み込んだ形にもなったと思います。ただ具体的な事例を見ていくと、まだまだ議論が必要になるようなことも散見されています。
例えば「類型①事業形態の高度化」の温室効果ガス排出削減量の評価について、ペットボトルの水平リサイクルを事例に取り上げられております。従来の処理方法との比較において、基準シナリオとしては①使用済みペットボトルの熱回収(適正処理シナリオ) ②使用済みペットボトルのカスケードリサイクル ③使用済みペットボトルの全国平均の処理割合(全国平均)の評価となります。機能単位には使用済みペットボトル1tの処理とペットボトルの1tの製造です。
事業シナリオでは、収集運搬を経産省国交省のCO2算定方法ガイドラインからCO2算出、破砕・洗浄・成形を容リ協のデータから、化石資源(石炭)の燃焼は環境省データベースから、電力は環境省の排出係数、ペット樹脂製造は容リ協から算定します。それに、基準シナリオ①使用済みペットボトルの熱回収、②使用済みペットボトルのカスケードリサイクル、③使用済みペットボトルの日本平均の処理を夫々算定していきます。
厳格化で考えていくと、夫々に活用するデータベースの適正さも議論が必要になっていくと思います。誰もが共通して考えられる、技術的知見が無くても判断できるような考え方の統一も必要になっていくと思います。ただ、この度の取り組みでは、これまでのリサイクルから一歩進めることであっても良いと思います。先の削減貢献量の議論も続く中で、まだまだ厳格化できないのは当然でもあるのでしょう。GHG削減への取り組みでは、ウォッシュ対策としてでもありますが、一方で削減に取り組む社会性重視の企業へインセンティブにも繋げたい思いもあります。同様にリサイクルに対して必要性は理解していても、コストアップや品質ダウンが受け入れがたい世の中で、先ずは少しでも後押しできることも重要だと考えます。