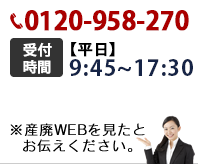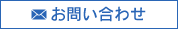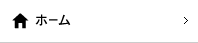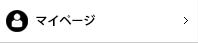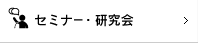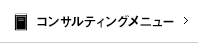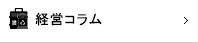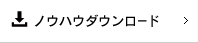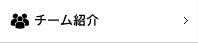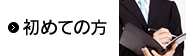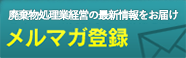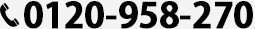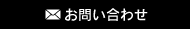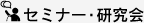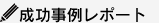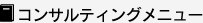経営コラム
廃棄物処理業は、サーキュラーエコノミーの潮流に如何に取り組むか⑤
2025年のサーキュラーエコノミーの取り組み方についての第5弾となります。
前回までの通り、2025年にサーキュラーエコノミーでのビジネス展開として、おさえるべき「高度化法」こと資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律についてとなります。
事業としては目標年度を7年と想定しており、優良産業廃棄物処理業者の更新期間を参考となっております。長いようで短いと言うべきか、事業可能性調査や協業先との調整、またファイナンス、そして遅れがちな工事まで含めると、事前準備期間の短縮が求められます。本件が、2025年7月現在で慌ただしく動いているのは、その背景もあって、ルールが正式に決まってではなく、ビジネスとして成功の確率を上げる為でもあると考えられます。一方で、10年ひと昔と言われた昭和や平成前半とは異なり、既に5年ひと昔となっております。時流が変わる前にビジネスの波に乗ることは重要な勝因でもあると思います。
類型は、①高度再資源化事業計画の認定 ②高度分離・回収事業計画の認定 ③再資源化工程高度化計画の認定の3つとなります。
類型① 高度再資源化事業計画の認定は、業の特例として「認定高度再資源化事業者は、一般廃棄物業許可(運搬・処分)、産業廃棄物業許可(運搬・処分)の規定に
関わらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為を業として実施することができる」となります。
認定基準としては
①事業の内容が法令、基本方針における内容と齟齬がないこと
・マテリアルリサイクルの場合、再生材の供給先が製品製造となっているか
・排出される温室効果ガスの削減効果があるか
②再資源化により得られる再生部品又は再生資源がその供給を受ける者の需要に適合していること
・書面により確認
③再生部品又は再生資源の大部分が当該者(供給を受ける需要者)に対して供給されること
・指標を用いて評価
・供給に係る契約書、事業連携協定等の書面により確認
認定基準からも明確なことは、出口に対してとなっていることです。過去のリサイクルには、この出口発想が無いことも多く、リサイクル材を作れても、その後の需要が無いことから、結果として事業が立ち行かないケースも多く見られたものです。「リサイクルしているから良いだろう」「埋め立てるよりも良い」「地球環境に良いことしている」、とこれらの発想が多く見られたものです。ただ、シンプルに言えることは、経済合理性が無いものは長続きしない、ということです。リサイクル材活用だからバージン材よりも高くて、質が悪くても仕方が無い、は通用せず、製造側にとっては常に競合環境で戦っており、質が良いものを適正な価格で供給することを目指しています。大量生産大量消費の時代は終わり、リサイクル推進は当然必要な流れでもあり、避けることはできません。しかし、サーキュラーエコノミーとしては、やはり循環経済であり、経済の輪が作られなければなりません。それ故、この類型①の基準も当然と言えるでしょう、