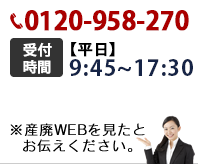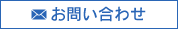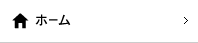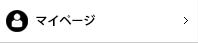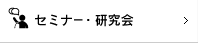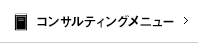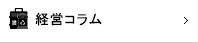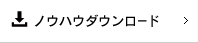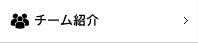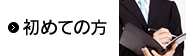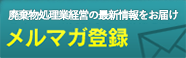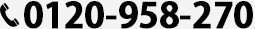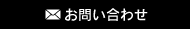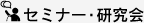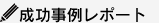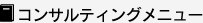経営コラム
廃棄物処理業は、サーキュラーエコノミーの潮流に如何に取り組むか③
2025年のサーキュラーエコノミーの取り組み方についての第三弾となります。
前回の通り、廃棄物処理業は、サーキュラーエコノミーの潮流に如何に取り組むか②
脱炭素化への寄与が背景にもあります。廃棄物単体でのCO2削減は全体の3.2%とインパクトに欠けますが、資源循環を踏まえると全体の36%の削減貢献可能とも言われております。更に進んでいるEUでは、再生材利用が拡大しており、再生材の質と量の確保にて資源循環の産業競争力を高めようとしております。
つまり、ビジネスチャンスと捉えるべきなのです。しかし一方で廃棄物処理業者が抑えるべきポイントとして、①「特に処分量の多い産業廃棄物業者の再資源化の実施状況の報告・公表」と②「国が一括して認定を行う制度から、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続きの特例を設ける」ということでしょう。①に関しては、対象となる規模も気になりますが、その目的も気になると思います。公表されるということは、再資源化を求める顧客にとっては別の選択肢を選ぶ要因になるかもしれません。また何よりも、廃掃法に基づかない処理施設が出来るということは、施設の立ち上げのスピードも大きく変わるものにもなっていきます。
これらはリスク的視点ではありますが、先ずはリスクの最小化でもあり、そのうえで機会の最大化でもあるでしょう。
基本方針は以下となります。
●基本方針の柱
効率的な再資源化:製造事業者と廃棄物処分業者が連携して、不要な焼却・埋立を削減
生産性向上:技術革新により、従来困難だった廃棄物の再資源化を拡大
工程の脱炭素化:再資源化のプロセス自体からの温室効果ガス排出も削減
●関係者の役割
国: 認定制度や情報基盤整備、支援策などで高度な再資源化を後押し
地方公共団体: 地域の事業者・市民を巻き込み、広域連携や分別収集等を推進。
廃棄物処分業者: 「主たる役割」として再生資源を製造事業者に供給できる体制を整備。
事業者: 再生資源を使いやすい設計や調達を行い、排出される廃棄物は分別・情報提供。
国民: 分別排出や再利用製品の選択など主体的行動が必要
●数値目標(2030年度)
循環利用率:入口19%、出口44% / 一人当たり天然資源消費量:11トン/人
年最終処分量:一般廃棄物320万トン(約5%削減)産業廃棄物780万トン(約10%削減)
温室効果ガス:廃棄物部門2,900万トン-CO₂程度
品目別目標:金属リサイクル▶倍増 家電四品目▶70.9% 電子スクラップ(e-scrap)▶2020年対比1.5倍
プラスチック▶ワンウェイプラ25%削減、再生利用倍増
方針の柱からは、製造事業者と廃棄物処分業者の「連携」と、「不要な焼却・埋立削減」、また「生産性向上」や「プロセスも脱炭素化」のキーワードからも、方向性の軸を読み取ることもできます。
関係者の役割にて、国の「認定制度」と「情報基盤整備」、地方公共団体では「地域の事業者・市民」と「広域連携」、事業者の「再生資源を使いやすい設計や調達」
そして数値目標にて、金属リサイクル、家電四品目、電子スクラップ、プラスチックと明記されており、特にプラスチックのワンウェイプラ25%削減となったことで、ターゲットも見えております。
廃棄物処理業にとっては、これらについてのリスクと機会を考えていく必要があります。